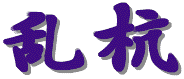|
7月12日、都城市立美術館で初日を迎えたメゾチント(銅版画)の展覧会「20世紀版画の巨匠“浜口陽三”展」を妻と2人で見た。久しぶりに心洗われる展覧会だった。
20世紀絵画の巨匠、パブロ・ピカソが、白磁器のような下地に、日本画で極細の線を引く時に使う「面相筆」で引いたような輪郭線が特徴的な藤田嗣治の作品の前に1時間以上も立ち尽くしていたという逸話がある。自分をピカソに例えるのは誠に恐縮だが、浜口の作品を見ながら、どうすればこのような表現がでるのか分からなかった。
木版画では、版木を彫刻刀等で削り、溝や窪みを付けることで、残った版木の表面に絵の具を付着させ、それを紙に写し取って作成するが、銅版画では、専用の様々な鋼製の刀で銅版に傷を付けるだけでなく、銅に反応する硫酸などの薬剤などにも浸して、表面を溶かして多様な表現をする。
「分かりやすい」技法の解説展示もあったのだが、どのような表現技術を駆使したのかと、貯めつ眇めつ凝視しても分からない。とまれ彼は、我が国画壇でも比類ない稀有の作家であると思う。
彼は、皆さんの中学・高校時代の美術の教科書に必ず載っていた、暗いバックに幾つもの赤いサクランボが浮かんでいるあの銅版画を作った作家だ。(写真下)

|
|
私は、彼の作品を高校2年生の修学旅行の時、皇居のお堀端、竹橋にある科学技術館での昼食休憩の時間に、引率の先生方に無断でそこを抜け出して、隣接する国立近代美術館で初めて見て強く心を引かれた。静寂な雰囲気と暗黒の背景、その中に無造作に置かれたサクランボに隠された深いメッセージに心引かれた、と言ったら「キザ」だろうか?
高校2年生の「僕」は、具体的に言葉として表現は出来ない不思議な「感慨」を持った。
そして、それから30年以上過ぎた「僕」は、再度、都城市立美術館で彼の作品に触れた。モチーフの大半は、サクランボ、ブドウ、レモン、テントウムシ。
彼は、これらの物言わぬモチーフを暗い闇のようなバックの中に浮かび上がらせて「超宇宙の無言の魂の叫び」を描こうとしたのではないかと思った。
ホワイト・パロット・シークリッド
何時もお世話になっている床屋さんが飼育して増やした熱帯魚の子供をいただいた。 こちらからは、昨年はウナギの稚魚、その前は子猫「モモ」を頂き、まるで我が家専属のペットショップみたいな床屋さんだ。
下の写真が不鮮明で恐縮だが、目の輪郭の金冠が顔面前の下の方だけ細くなっていて、小さな身体に似合わず挑戦的に見える。熱帯魚飼育のベテランである妻は「このスネたような表情がいい。」と評した。

|